食品表示検定初級のCBT方式を受験してきました

2022年より初級と中級はCBT方式(コンピュータを使った試験)が導入され、今回私は実際に食品表示検定試験・初級のCBT試験を受けてきました。
受験しての感想と、メリットとデメリット、また今までのマークシート式試験との試験問題内容の違いを紹介していきます。
試験概要
今回私は食品表示検定試験・初級のCBT試験を受験しました。
| 受験科目 | 初級 |
|---|---|
| 料金 | 5,280円(税込) |
| 受験日 | 2022年6月4日(土) |
CBT方式とは
「そもそもCBT方式ってなんぞ?」って人のために簡単に説明しますと、Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」の略称で、コンピューターを使用した試験方式です。
試験会場に用意されたパソコンを利用して、マウスで選択肢をクリックして回答を進めていきます。
既にIT資格試験ではCBT方式は積極的に導入がされていましたが、食品表示検定試験では2022年度から初級と中級はCBT方式に正式になりました。
CBT試験の流れ

当日のCBT試験の基本的な流れになります。
- 1. 受付
- 2. 受験者情報に署名
- 3. 本人確認(本人証明書必須!)
- 4. ロッカーに全荷物預ける
- 5. 受験
- 6. 試験結果を印刷して終了
ざっくりと書きましたが、現場にはサポーター的な対応者が数人いますので、わからないことがありましたら質問することも可能です。
持ち物
試験会場内への持ち物は、本人証明書(免許証)、ロッカーキー、ボールペン、メモ用紙になります。
ボールペンとメモ用紙はサポーターから支給されます。(試験終了後は返却)
当然ですがスマホは持ち込めません。
ここら辺の詳細についても受験日が近づくと、メールで会場アクセスや持ち物等の詳細情報も送られてきますので安心してください。
実際にCBT方式を受験しての感想
ほぼ問題なくスムーズに最初から最後まで集中して問題を解くことができました。
いわゆる人が多い受験会場であるとんでもないハプニングなどはありませんでした。
マークシート式の試験問題の違い
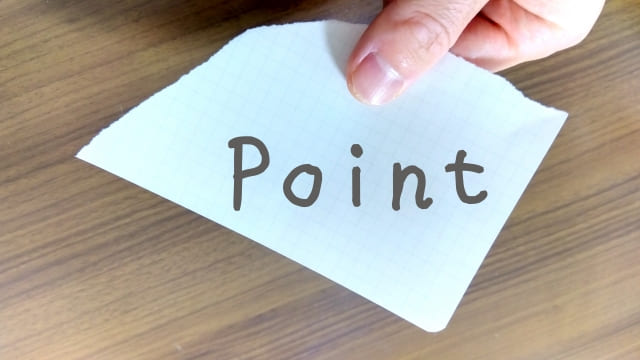
少し実試験についての突っ込んだ話をしたいと思います。
今までのマークシート式の試験では、教科書でいう第1章の「食品表示は消費者と事業者をつなぐ架け橋」から始まり、第1章の文章問題が終わると「スーパーの農産物売り場での表示」などの画像問題がひとかたまりで出題される流れが一般的でした。
しかしながら、CBT方式はほぼランダムでした。
ここで「ほぼ」と言ったのは、全75問のうち63-65番は、教科書でいう「その他の食品表示やマーク」のマークを問う問題で、66-70番は1つの表示に対して5箇所問いがある今までのマークシートと同様の構成だったからです。
以降も含めてその他はランダムでしたので、63-70番に関しては食品表示協会がどうしても出題したかった箇所なのかもしれません。
CBT方式のメリット
実際にCBT試験を受験してメリットを書いていきます。
ちなみに私は都内在住なので都内で受験しました。
- ・受験日を約1ヶ月の中から選択できる
- ・急な予定が入っても受験日時を変更できる
- ・都内だと会場がいろいろなところにあるので便利
- ・えんぴつ音など周りの音が気にならない。防音ヘッドホンがある
- ・試験画面の文字の大きさを変えられる
後はCBTならではと言いますか、解答状況という項目があるので、後でやる問題にチェックを入れることができたり、やり残した問題がないかも一目でわかる仕様になっています。
マークシートのように問題の解き忘れの事態もかなり減るのではないでしょうか。
CBT方式のデメリット
実際にCBT試験を受験してデメリットを書いていきます。
- ・使い慣れないマウスを操作することになり慣れるまで大変
感想としては、圧倒的にマークシート試験よりもCBT試験の方がメリットがありました。
その他
試験場にはカメラもありますので、カンニングもできません。
試験結果
試験結果は2022年7月22日(金)にマイページで確認ができます。
この辺りの詳細についても、最後に試験結果レポートとして試験後の詳細が書かれたレポートが渡されます。
最後に
以上が今回CBT試験を受けた感想になります。
圧倒的にマークシート式よりもメリットが大きく、何より自分の都合で日時を決定、変更ができるのも大きいですね。
是非、試験を受けるか迷っているあなたも受験に挑戦してみてください。
